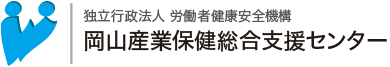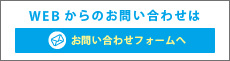相談員便り
2025年 熱中症予防には、どうして塩分が必要か?~体にとって塩分が必要な理由を改めて考えてみませんか?~(濱本貴史相談員)
2025年の夏、 6~8月の平均気温は全国的に平年より高くなる見込み(気象庁発表)で、5月1日~6月29日までの搬送件数は18,133件、令和6年と比べ約2倍のスピードと発表されました(総務省消防庁発表#1)。
#1:総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html
このような例年を超える猛暑ですので、私が産業医を務める企業においても屋外作業後に体調不良により救急搬送される方もわずかにいました。そういった場合、我々産業保健職は熱中症疑いの方へ作業内容や飲料摂取等のヒアリングをし、要因を検索します。すると最近の熱中症発生要因には共通点があることが判明しました。驚くことに、2例で塩分入りの飲料を摂取していなかったということが分かりました。
これを聞くと、「塩分をとることは小学生でも知っていますけど、どうして知らないんですか?」、「知らないわけないでしょ!!」とつい責めたい気持ちとともに、どうしてこんなことになるかという純粋な疑問が出てきました。小学生すら知っているにもかかわらず、なぜ?
当該者に塩分を摂らなかった理由を聞いたところ、「熱中症の予防に塩分が必要なことは知っているが、持病を悪化させたくなくて塩分を制限している。だから日常の食事だけではなくて、作業の合間にとる水分補給も塩分がないものを意図的に摂っている」とのことでした。
真面目過ぎるがゆえ、塩分がなぜ必要なのか理解されていないがため、こんなことになってしまうのかと驚きました。
健康のために塩分を制限するということは必要かもしれませんが、塩分制限することで、逆に倒れて働けなくなってしまっては本末転倒です。確かに一見すると理にかなっているように思えますが、過度に制限をすると熱中症で倒れてしまうリスクがあるということです。塩分を摂らなさすぎるのも駄目だし、摂りすぎも駄目、何事もバランスです。
屋外や暑熱職場で多量の発汗を伴う場合、熱中症予防には必ず塩分を摂取するようにしましょう。万が一塩分が取れない健康状態ということであれば、主治医や職位者に相談するようにしましょう。どうやっても塩分入りの飲料がとれないということであれば、熱中症リスクのある職場での労働は諦めないといけないかもしれません。
参考までに、この事例に対して私が従業員に提供した情報を共有します。
①熱中症予防として、何故、塩分が必要なのか?
汗とともにNaが減少するので、必ずNa摂取が必要。
塩分がないと体内に水分が保持できず、体温を冷却するための効果的な汗がかけなくなるから。
塩分摂取ができないほどの健康状態であれば、暑熱職場での就労有無を検討。

②熱中症予防として、どのくらい塩分が入った飲料が望ましいか?塩飴で塩分を摂取するのであれば、どのくらいの塩分量が望ましいか?

熱中症予防と「休憩室」、「休養室」、「外勤者の休憩」について(横溝浩相談員)
平成30年の西日本豪雨災害から7年が経ちました。
私の事務所のある倉敷市真備町は復興が進み、災害当初の瓦礫の山も片づき、元の風景に戻りつつあります。被災当時は、濁流が運んできた土砂や粘土質の土が乾燥して発生する微細な粉じん、瓦礫の撤去により発生する粉じんの飛散だけでなく、35℃以上の高温にも悩まされました。
高温が続く中、若いボランティアの方々が、15分間瓦礫の片付け作業を行い、15分間休むという熱中症予防対策を行っていた光景が記憶に強く残っています。また、自衛隊員の方々は、ヘルメット着用と迷彩服姿で水を含んだ重い畳を片づけて処分してくれました。非常に暑く、重労働だったと思います。感謝しています。
私はサラリーマン時代を含めると、ほぼ半世紀労働安全衛生の仕事に就いてきました。今では一月当たり20日は企業様を訪問する労働安全・衛生コンサルタント業務を行っています。月間の車での走行距離は平均約1600㎞です。
ここで困るのが夏場です。以前は喫茶店などで昼食と休憩をしていましたが、その喫茶店が姿を消してしまい、ファミリーレストランがあればいいのですが、無い地域では、道の駅やスーパーマーケット、コンビニの駐車場で休憩しています。ここには日影がありません。車のエンジンをかけて休憩するのもいいですが、「地球温暖化、環境に悪い」、「騒音問題」、「ガソリン価格の高騰」もあり、できるだけ窓を開けて、エンジンを止めて休んでいます。
こんな時に思い出すのは、5年程前のことです。スーパーマーケットの駐車場でお昼休みをしていると、若い女性が車の後部座席の方に何やら大声で話しかけていました。どうやら車のキーを1歳位のお子さんが持ったまま車内に閉じ込められてロックされ、ドアが開かないようでした。
JAFに救援を求めたのですが、到着まで40分程度かかるとのことでした。そこで、私は熱中症が起こるのは確実と思われたので119番を提案しました。しばらくすると、救急車と消防車が到着して、消防隊の方が車の後部座席のガラスを割って救出してくれました。一件落着でホッとしました。
駐車場などで休憩するのは、この猛暑ではそろそろ限界かもしれません。
2025年6月1日より、「職場における熱中症対策の強化」について改正労働安全衛生規則が施行されました。また、働き方改革関連法により、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働は、上限が年間960時間に規制されました。
猛暑における休憩時の大型車両の停車場所には課題があります。また、労働衛生に貢献してくださっている健康診断(健診車)の大型車、夏場の住民健康診断も屋外のテントの下で受付をされている場合があり、スタッフの方々の熱中症予防対策も重要と思います。その他、配達業務、交通整理の方々も同様と思います。
前置きが長くなりましたが、熱中症予防に関係する労働安全衛生規則について確認しておきたいと思います。「休憩設備」と「休養施設」は以下のように定められています。
「休憩設備」労働安全衛生規則
第613条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
【解釈例規】休憩の設備(第613条関係)の解釈例規(令3・12・1基発1201第1号)
事業場ごとに、休憩室の広さや、各事業場のニーズに基づく休憩室内に備えるべき設備については、衛生委員会等で調査審議、検討等を行い、その結果に基づいて設置することが望ましい。
「休養室等」労働安全衛生規則
第618条
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
【解釈例規】
本条は、病弱者、生理日の女子等に使用させるために設けるものであること。
(昭和23・1・16基発第83号)
休養室等(第618条関係)の解釈例規(令3・12・1基発1201第1号)
エ 休養室等(第21条関係)
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けなければならない。休養室又は休養所は、事業場において病弱者、生理日の女性等に使用させることを趣旨として設けられるものであり、長時間の休養等が必要な者については、速やかに医療機関に搬送する又は帰宅させることが基本であることから、専用設備として設けなくとも、随時利用が可能となる機能を確保することで足りるものであること。
なお、休養室又は休養所では、労働者が床することが想定されており、プライバシーの確保のために、入口や通路から直視されないよう目隠しを設ける、関係者以外の出入りを制限する、緊急時に安全に対応できる等、設置場所の状況等に応じた配慮がなされることが重要であること。
また、以下に「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」基発0420第3号 (令和3年4月20日)、一部改正 基発0726号第2号(令和3年7月26日)、一部改正
基発0520第7号(令和7年5月20日)を抜粋いたしました。
(2) 休憩場所の整備等
労働者の休憩場所の整備等について、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。
ア 高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設けること。また、当該休憩場所は、足を伸ばして横になれる広さを確保すること。
イ 高温多湿作業場所又はその近隣に氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設けること。
ウ 水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行えるよう高温多湿作業場所に飲料水などの備付け等を行うこと。
現状では、「休憩設備」はあっても「休養施設」が無い企業様が多いようです。
常時使用する労働者の人数を規定していますが、私は、「休養施設」は人数に関係なく、男性用と女性用を分けて設置してほしいと思います。敷地や予算に限りがあるかと思いますが、熱中症により救急車を呼ぶ事態が起こるかもしれません。そのためにも「休養施設」を確保していただけたらと思います。上記の解釈例規から考えると、緊急対策として「会議室」や「応接室」を「休養施設」に代用しても良いのではないかと思います。いかがでしょうか。
まだまだ猛暑が続くようです。
皆様、ご安全に!!
横溝労働安全衛生コンサルタント事務所
岡山産業保健総合支援センター 産業保健相談員
労働衛生工学相談員
横溝 浩
研修会のご案内
研修会についてはこちら
https://okayamas.johas.go.jp/training/
産業医研修会についてはこちら
https://okayamas.johas.go.jp/category/training/ipt/
労働衛生コラムNo.15 『治療と仕事の両立支援が努力義務になります』
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(略称労働政策総合推進法)に、治療と仕事の両立支援に対する事業主の責務が明記されました。
施行期日は、令和8年4月1日です。
https://okayamas.johas.go.jp/column-no15/
「中皮腫パネル」について(労災疾病等医学研究普及サイト)
石綿(アスベスト)は、かつて建設資材や自動車部品などに利用されてきましたが、石綿繊維を吸入すると肺がんや中皮腫など石綿関連疾患発症の原因となるため、現在は製造・使用等が原則禁止されています。
石綿関連疾患の診断及び石綿ばく露所見の判定にはエックス線写真の読影等が必要となりますが、その判断が難しい事例が多く、医学的な知識・経験に加え、石綿ばく露等についての知識も必要となります。
労働者健康安全機構では、最新の医学的知見や診断技術を踏まえた石綿関連疾患の診断方法、石綿ばく露の所見に関する読影方法及び労災補償制度の取扱い等についての研修を行っています。
今回はその中の一つである「中皮腫パネル」についてご紹介します。
「中皮腫パネル」は、中皮腫診断に携わる医療関係者を対象とし、中皮腫の確定診断が困難であった症例について、パネル形式により参加者全員で診断を行うものです。
令和7年度は9月13日(土)に広島大学において開催を予定しています。
労災疾病等医学研究普及サイト
https://www.research.johas.go.jp/asbestokenshu/
https://www.johas.go.jp/kenkyu_kaihatsu/rosaisippei13bunya/tabid/398/Default.aspx