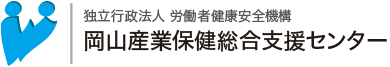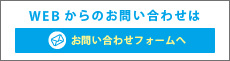1.相談員便り
産業界におけるアスレティックトレーナーの役割(乍智之相談員)
みなさまはアスレティックトレーナー(以下:JSPO-AT)という資格をご存じでしょうか。ほとんどの方はご存じないと思いますが、この資格を取得するには、まず中央競技団体か都道府県スポーツ協会の推薦が必要です。(近年では一部の承認校でも可能です)
私は日本野球連盟の推薦枠3名のひとりとして、1996年に始まった養成講習会の1期生です。岡山県スポーツ協会からの推薦枠は毎年ひとりという狭き門であり、合格率も(正式には公開されていませんが)HPを見ると20~25%(2007~2010年)で推移している、なかなか大変な資格です。
私は元々旧川崎製鉄水島硬式野球部に22年間、現役選手・コーチ・JSPO-ATとして在籍し、引退した2003年から現在の健康管理の部署に配属されました。当時、国内産業界にJSPO-ATは存在せず、「何の資格?何ができるの?」と聞かれることが多く、私自身も会社の中で何ができるか手探り状態のままゼロからのスタートでした。
そのような中、2004年に安全に長く元気で働くための体力を「安全体力®」と定義したことで進む方向が見えてきました。現在は約4,000名の従業員の「安全体力®」のレベルを保つ取り組みと、「安全体力®」が低下した従業員の問題を改善する取り組みを行っています。(詳しくはHPをご参考ください)
近年、「転倒」や「腰痛などの筋骨格系疾患」に代表される行動災害が大きな問題となっています。設備リスクの対策だけでは不十分であることがわかってきました。スポーツにおけるケガの原因は、間違った投げ方や走り方、または体力低下が主な原因です。再発予防のためにはフォーム修正、トレーニング、コンディショニングなどが必要です。
同様に、身体活動を伴う労働現場においても、情報機器の使用や重筋作業時の体の使い方(フォーム)、運動不足や過去のケガの後遺症による筋力や柔軟性の低下といった内的要因にもアプローチしない限り、ケガを減少させることは難しいと考えています。まさにアスレティックトレーナーが貢献できる分野です。
JSPO-ATの役割は以下のように定義されています。実は、赤字の部分を変更すると、産業JSPO-ATとして労働者を対象とした役割にもなることに気づきました。
「スポーツドクター(産業医)やコーチ(産業保健スタッフ)と緊密な協力のもと、スポーツ活動(業務)中の外傷・障害予防、コンディショニングやリコンディショニング、安全と健康管理、医療資格者へ引き継ぐまでの救急対応を行い、スポーツをする(働く)人の安全と安心を確保したうえで、(作業)パフォーマンスの回復や向上を支援する資格」です。
弊所では、2020年から柔道整復師、理学療法士の3名体制で「安全体力®」の取り組みを行っています。アスリートを支えるためにJSPO-ATが必要なように、働く現場でも産業界のアスリートである社員の「安全体力®」を支える専門家の配置が増えることを期待しています。
ストレスを活用して健康になる~ストレスは健康に害でないと信じることで健康に~(濱本貴史相談員)
一般的に、ストレスは健康に良くないので、減らしましょうと言われることが多くあります。医師も同様で、ストレスは健康に良くない、ストレスによる心身の不調、例えば血圧や自律神経失調を避けるためにストレスは避けましょうと教えられます。
しかしながら、私は企業の専属産業医として、ビジネスの最前線でプレッシャーにより心身の不調をきたし療養に至る人を見ることもありますが、逆にプレッシャーを糧に成長につなげ、最前線で活躍されている人にも多く接する機会があります。長期にわたり過度なストレスを受けた方は不調につながる可能性が高まるでしょうが、日ごろの産業医の経験よりすべての方には当てはまらないと感じています。
ストレスに向かい合い、療養から学びを得て、療養の意味を見出している事例です。
職場の人間関係を契機にメンタル不調に陥った方は、療養の発端となった人間との関係を避けるべく、異動等の業務上の配慮を求めようとします。彼らは職場復帰時、療養の発端となった人間との関係を避けようと、異動等の配慮を求められることが多くあります。ですが産業保健職のサポートにより踏みとどまり、環境や他者に依存することなく自身の内省につなげます。今回の経験から何を学んだのか、学びを生かして次からどのように振る舞うか、主に自身の向き合い方を変えるなど療養に意義を見出すことで、長期に渡り職場で成果につなげる方がいます。
一方で、ストレスを害ととらえ、避けようとした療養者の事例です。
職場の人間関係を契機にメンタル不調に陥った方は、療養の発端となった人間との関係を避けるべく、異動等の業務上の配慮を求めることが多くあります。本人の求めに応じストレスを避ける配慮を行うと、療養に入った方々は療養の契機となった人間だけでなく、あらゆるストレスを避けることになり、最終的にその職場に居場所がなくなり、職を失うという転機をたどった方は少なくありません。
皆様に伝えたいのは、ストレスを感じる出来事であっても必ず良い側面とそうでない側面があり、ポジティブに捉えるか、そうでないかで予後が大きく変わるということです。
ここから読み取れる教訓として、ストレスの捉え方さえ変えれば、誰しも人生を変えることができると私は信じ日々支援をしています。
参考までに興味深い研究を紹介します。
(参照:ケリー・マクゴニガル: ストレスと友達になる方法、 TEDTalks、2013年)
米国で3万人の成人を対象に、8年間、追跡調査をした研究です。
参加者には次の2つの質問をし、死亡率(予後)を検討した研究です。
(1) この1年間でどの位ストレスを感じましたか?
(2) ストレスは健康に害になると信じますか?
これらの3万人の調査で予後が最もよかったのは、「ストレスを感じたが害にならないと信じている方々」、一方で予後が最も悪いのが「ストレスを感じストレスが害になると信じている方々」でした。ここからもストレスの捉え方が大きく影響しているということが見て取れるかと思います。
2.研修会のご案内
研修会についてはこちら
https://okayamas.johas.go.jp/training/
3.労働衛生コラム『情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて』
近年のハードウェア・ソフトウェア双方の技術革新により、職場におけるIT化はますます進行しており、情報機器作業を行う労働者の範囲はより広くなり、また、作業形態はより多様化していることから、情報技術の発達への対応及び最新の学術的知見を踏まえ、「VDT作業」を「情報機器作業」に置き換え、令和元年7月にVDTガイドラインは、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(情報機器ガイドライン)」に改正されました。
詳細はこちら
https://okayamas.johas.go.jp/column-no13/
4.「病職歴データベースを活用した研究」について
労災病院グループでは、全国の労災病院に入院された患者さんにご協力をいただき、それまでの仕事や生活習慣等に関する情報を収集しています。その収集した情報は、データベース化して職業と疾病との関連性について研究を行い、その研究成果は就労者の健康の保持増進及び疾病の予防・治療・職場復帰支援に活用しています。今回は「病職歴データベースを活用した研究」についてご紹介します。
https://www.research.johas.go.jp/bs
今般、病職歴データベースを用いて、日本人男性における有害化学物質を扱う職場での就業年数とがんリスクについて解析した結果が「Occupational and Environmental Medicine(2023;80:431-438.)」にて報告されました。有害化学物質を扱う職場での就労期間が長いほど、複数のがんのリスクが高いことが明らかになり、特に喫煙歴と危険な化学物質を扱う仕事との組み合わせは、がんのリスクをさらに高める可能性があるため、がんを予防するには、職場での化学物質管理について対策が必要であることが示唆されました。
研究論文が以下のリンクからご覧になれます。
論文タイトル:『Length of employment in workplaces handling hazardous chemicals and risk of cancer among Japanese men』(深井航太先生)
https://www.research.johas.go.jp/bs/#results
5.「早期復職」について
現在、がんは日本人の死因のトップであり、国民の2~3人に1人は生涯の間に一度はがんと診断されます。また、がんと診断された方の3人に1人は就労可能な年齢にあたり、社会の高齢化が進む中、がんと診断された後も仕事を続ける労働者は、今後増えていくことが予想されます。
がん患者さんが復職するうえで最も重要なことは、体力の維持・増進とされており、そのためには「運動療法」と「食事療法」が効果的であると考えられています。
平成30年7月から令和5年3月まで実施した「消化器癌(胃癌、大腸癌)手術患者における蛋白質の補充と運動療法が骨格筋の増加に及ぼす影響に関する研究」では、がん治療で手術を受ける患者さんを対象として、持久力や筋力を強化する「運動療法」と、最適な蛋白質を摂取する「食事療法」を手術前から一定期間実施し、退院後9週目まで血液検査や体力測定等を行うとともに、復職の状況も調査しました。
令和5年6月までに登録された、消化器癌手術患者における「運動療法」に蛋白質補充を付加する試験群と対照群の計50症例について、統計解析を実施しました。
本研究では統計学的有意差を示すには至りませんでしたが、術後の運動療法及び栄養摂取の介入により、骨格筋量、筋力および歩行能力は、退院後9週目には術前値と比較して同等以上に回復・向上しました。これらの介入が術後のADL(日常生活動作)回復を早め、早期復職を含む社会復帰につながる可能性を前向き試験において示せたことは非常に意義深いものと考えています。
https://www.research.johas.go.jp/souki2018/index.html
6.岡山県産業看護部会からお知らせ
岡山県産業看護部会では、企業内で実践する女性の健康管理について研修会を開催いたします。ご興味がある方は、ぜひご参加ください。
【研修会概要】
日時:4月20日(日)10:30~12:00
会場:(株)中電工 岡山統括支社(岡山県岡山市南区浜野4丁目2−7)
演題:女性の健康管理
講師:長井聡里 (株式会社JUMOKU 代表)
【申込フォーム】
https://forms.office.com/r/hTBPabiPN2
申込期間:3月7日(金)まで
次回の第207号は2025年3月17日に配信予定です。