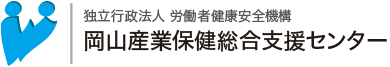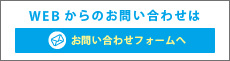相談員便り
外国人労働者の現在地と情報の伝え方のひと工夫(勝田吉彰相談員)
国内の労働力不足もあり、外国人労働者は増加する一方です。
出入国在留管理庁統計の在留外国人数(総数)では3,588,956人1)、厚生労働省統計の外国人労働者数では2,302,587(対前年比12.4%増)2)という数字になっています。
1)https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html
2)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html
彼らの在留資格のなかでも多くを占めるのが「技能実習(廃止され育成就労制度へ移行が決定)」「特定技能」「技能・人文・国際業務(通称 技人国、ホワイトカラー職のイメージ)」です。このなかで、ある程度のスキルを身につけた「特定技能」在留資格についての現在地を紹介しましょう。
「国内の人材不足を解消し、特定の産業分野で活躍する外国人を受け入れること」とうたわれるこのカテゴリーに入るのは、技能実習(育成就労に移行)を経てステップアップするか、試験を受けて合格するとビザが得られます。
特定技能1号と2号に分かれ、前者は1年ごとの更新を原則とし、 介護分野・ ビルクリーニング分野・工業製品製造業・建設分野・造船・舶用工業分野・自動車整備分野・航空分野・宿泊分野・自動車運送業分野・鉄道分野・農業分野・漁業分野・飲食料品製造業分野・外食業分野・木材産業分野から成ります。家族帯同は認められていません。
後者の2号ではより高度のスキルをもつエキスパートのような存在(たとえば建設業ならば現場監督ができるレベル)で家族帯同も可能となります。
数の多い特定技能1号では総数28万名あまりで、その出身国はベトナム>インドネシア>フィリピン>ミャンマー>中国>ネパール>カンボジアの順となっています。外国人雇用協議会のセミナーなどでは、今後伸びが期待されると紹介されるミャンマーですが、軍事政権が徴兵制をはじめて出国が不透明なところが懸念点とされています。
「ひと文字もわからない言語」で情報を伝えるにはどうするか
先述の外国人労働者の国籍について、将来増加が見込まれる国があります。
昨年、筆者が参加した外国人雇用協議会の交流会で相談ブースを出していたのはミャンマー・インドネシア・バングラデッシュ・インド・モンゴルといった国々の関係者でした。そして日本語学校の関係者と話せば、いま現地に進出して新たに日本語学校を開設する動きはネパールがそろそろ頭打ちで次はバングラデッシュだという声も聞きます。
こうした国々に共通するのが「(われわれにとって)一文字もわからない言語」を使うことです。ミャンマー語・ベンガル語・ネパール語・クメール語・・・
ではこうした国々からの労働者が我々の産業保健の現場で目の前に現れるとき、どうやって情報を伝えるか。筆者の活動から着想を得たところを紹介します。
筆者は外国人労働者研究のひとつとして、近年増加が著しいネパール人労働者をめぐる現状を調査していましたが、その中で「日本の生活について基本的な情報が得られぬまま現実に直面して高ストレスにさらされる、情報不足問題」が明らかになりました。
それを教えてくれたのが日本国内で発行される唯一のネパール語紙であるネパリ・サマチャ紙のティラク・マッラ編集長。このご縁で、同紙への連載を続けています。

最初開始時は英語で出稿してネパール語に訳していただいていたのですが、途中から、生成AI(chatGPT)で直接ネパール語で出稿して、おかしな所を修正してもらうようにしています。
したがって現在は「おかしな所を(ご縁のある)ネイティブになおしてもらう」という属人的な部分があるのですが、この属人的な部分を抜きにできるようになれば、「一文字もわからない言語」で情報を伝えることも夢ではなくなります。
たとえば、「イスラム教徒の労働者に、我が社の社員食堂のメニューから選択する方法をベンガル語で伝える」とか「我が社のヒンズー教徒の〇〇カーストと〇△カーストの労働者に班分けを指示して、〇〇区の〇△機械で巻き込まれ労災を発生させないよう協調して作業する手順を伝える」「インフルエンザの流行が警報レベルになったので〇〇と〇〇という症状がでたらすぐに申し出て、工場内の〇〇と〇△には行かないように」とか・・・
いま、書店やAmazonサイトには、AIをつかった翻訳の参考書がいろいろ紹介されています。筆者はいままだ勉強中ではあるのですが、その手順の骨格を紹介します。
*************************************
(AI翻訳の手順)
• 前工程:翻訳仕様の設定/設定条件の記述
目的・対象読者・用語の明示
原文の提示
• 制作工程:プロンプト(指示文)の入力
• 後工程:エラーチェックのプロンプト入力
正確性エラー
流暢性エラー
文体エラー
フォーマリティエラー
************************************
要約、翻訳したい原文の日本語を入れる前に、目的や対象者などの情報を入れ、適切な専門用語を提示するプロセスが重要で、翻訳文が出力されてからエラーチェックも必要になります。
AIによる翻訳は「多言語モデル」というもので、google翻訳などの「機械翻訳」とは異なる仕組みで、AI自体が内容を把握してニュアンスもいろいろ対応できますし、また、修正を重ねればAI自体が学習してもゆきます。
会社の外国人スタッフからフィードバックももらいながら修正してゆけばAI自身も賢くなってゆき、〇〇会社の産業保健の最適化した最強のツールになってゆくかもしれません。
《勝田相談員について》
https://okayamas.johas.go.jp/consultation/advisor-profile/#katsuda_yoshiaki
労働衛生の三管理:問題を発見・予見する視点と、その対策を考える視点(田口豊郁相談員)
私が駆け出しの作業環境測定士の頃(1980年代初頭)、ある研修会で「労働衛生の三管理」を次のように学びました。
①作業環境管理(Working Environment Control)
②作業管理(Work Practice Management)
③健康管理(Health Care)
各々の「管理」を英語のコントロール、マネジメントおよびケアと考えることで、労働衛生の三管理の意味が腑に落ちたと記憶しています。
すなわち、労働衛生の三管理とは、
①コントロール:人以外のものを管理(制御)すること
②マネジメント:人の集団を管理(働き方を)すること
③ケア:一人ひとりをその人に合ったように管理(医学的に)すること
――で、働く人一人ひとりの健康と安全を確保することです。つまり、人以外(環境・設備等)に働きかけるのが「コントロール」、人に働きかけるのが「マネジメント(集団)」および「ケア(個人)」ということになります。
しかし、最近の労働衛生関係のテキストでは、このような記述は見当たらなくなりました。「労働衛生の三管理」を正しく理解するために、「コントロール、マネジメント、ケア」を広めたいと思い、この原稿を書きました。
生産工程の複雑化や多様化が進み、事業場内の危険性・有害性(リスク)も多様なものとなっています。
これまでのように法令に規定される危害防止基準を遵守することに加えて、企業が自主的に事業場内の不安全状態・不安全行動等のハザードを見つけ出し、それらのリスクを評価し、これらに基づき必要な対策を講じるという事前の予防措置(労働安全衛生マネジメント・リスクマネジメント)が求められるようになりました。
事業場における化学物質管理体制の強化を目的として、化学物質規制体系の見直し(自律的な管理を基軸とする規制への移行)が急速に進められています。
「化学物質の自立的管理」においても、労働衛生の三管理は基本的な視点です。リスクアセスメントの実践に当たって、「労働衛生の三管理」の各々の視点から、「ハザード」を特定する、さらにリスクアセスメント後の「リスク対策」を「労働衛生の三管理」の各々の視点から、検討・実施することが有効です。
問題を発見・予見する視点および、その対策を考える視点しての「労働衛生の三管理」(「コントロール・マネジメント・ケア」の視点)は、これからの安全衛生活動の中で、益々、有効かつ重要となるでしょう。
また、「コントロール・マネジメント・ケア」の視点は、「労働衛生管理」だけでなく、「労働安全管理」にも当てはまります。「労働安全衛生の三管理」と言うことができると考えます。
【参考文献】
KOSHI S (1996) A Basic Framework of Working Environment Control for Occupational Health in Japan. Industrial Health. 34(3).
https://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth1963/34/3/34_3_149/_pdf/-char/ja
《田口相談員について》
https://okayamas.johas.go.jp/consultation/advisor-profile/#taguchi_toyohiro
研修会のご案内
研修会についてはこちら
https://okayamas.johas.go.jp/training/
産業医研修会についてはこちら
https://okayamas.johas.go.jp/category/training/ipt/
予防医療についての研究
労災疾病等医学研究普及サイトのご案内
「予防医療モデル事業」について
全国9か所の労災病院に設置されている治療就労両立支援センターでは、疾病の予防および増悪防止を目的とした生活指導、運動指導、栄養指導といった、勤労者の健康確保を図るための予防医療活動を行っています。
また、この予防医療活動によって集積した事例から、次の5つのテーマに基づいた予防法・指導法の研究開発を行い、全国の事業場に向けてそれらの成果の周知と普及に努めています。
■生活習慣に伴う疾病
(メタボリックシンドローム、高血圧、喫煙、飲酒など)
■作業動作に伴う運動機能障害
(関節痛、腰痛、頸肩腕症候群など)
■高齢勤労者特有の健康障害
(ロコモティブ症候群、サルコペニアなど)
■勤労女性特有の健康障害
(更年期、ライフステージ、勤務形態など)
■ストレス又は不眠(睡眠障害など)
これまでの研究課題では、SNSで話題を集めた「交代勤務者及び深夜業務におけるコンビニメニューの選び方に関する指導法の調査・研究、普及」や「勤労女性の飲酒実態調査及びアルコール健康障害予防のための適正飲酒の指導法の検討」等、皆様の健康維持に役立つ研究を行いました。
これらの研究成果は、47都道府県に設置されている産業保健総合支援センター等を通じて事業場や働いている皆様にご活用いただいています。
また、上記の研究は当機構が発行する情報誌「産業保健21」でもご紹介していますので、併せてご覧ください。
■産業保健21
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/johoteikyo/tabid/128/Default.aspx
予防法・指導法についての出張講演のご依頼は下記連絡先までお願い致します。
なお、事情によりご依頼をお受けできない場合もありますのでご了承下さい。
労働者健康安全機構
勤労者医療・産業保健部勤労者医療課 勤労者医療班
(Tel)044-431-8641
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)から調査研究成果物のご案内
①調査研究報告書
「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」
https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku182.html
②マニュアル
「精神障害者保健福祉手帳を所持する方の就業の状況と企業が取り組む職場の配慮・措置」
https://www.nivr.jeed.go.jp/research/kyouzai/kyouzai85.html
高齢・障害・求職者雇用支援機構においては、令和4~6年度に実施した「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」の成果物として、①調査研究報告書及び②マニュアルを令和7年3月末に公表しました。ホームページからダウンロードできますので、是非御活用ください。