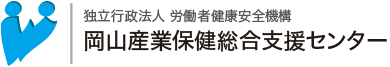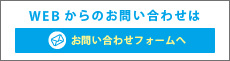相談員便り
多文化共生を考える-日本人メジャーリーガーと外国人労働者、日本人ファーストを例にして-(神田秀幸相談員)
相談員 神田秀幸
岡山大学学術研究院医歯薬学域公衆衛生学
日本人メジャーリーガーの活躍は今季もめざましかった。海の向こうの日本人選手の奮闘が、私たちを勇気づけたり励ましてくれたりした。シーズン中は毎日が楽しみだった。
現役のサムライ投手が体格の大きいパワーヒッターを空振りさせる姿は、日本人として胸が熱くなった瞬間だった。また、イチロー選手が、アジア人として初めて米国野球殿堂入りを果たした事を誇らしく思ったのは私のみならず、多くの人が同じ気持ちだったに違いない。
一方で、ここ岡山でも、コンビニで働く店員さんに外国の方をよく見かけるようになった。レジでの日本語コミュニケーションは全く問題なく、時に、名札を見て初めて外国人であることに気づく場面もある。異国の地で働いている姿に、とても感心する。
私は少しばかり外国留学経験を持つが、異国で生活するだけで精一杯で、まして働く・お金を稼ぐ能力なんて無かった。彼らのたくましさに敬意を表したい。そんな中で、日本人ファーストを唱える国民世論が一定の支持を得て、民意として表れてくるようにもなった。
アメリカ人にとって、日本人メジャーリーガーの活躍はどう映るだろうか?
メジャーリーグを一層盛り上げてくれたと喜ぶオーナーもいれば、日本人選手の活躍で出場機会を奪われた選手もいることだろう。アメリカファーストの思いを持つ人は日本人選手を苦々しく思う人もいるに違いない。
一方、日本人にとって、外国人コンビニ店員さんはどう映るだろうか?
働いてくれて助かったと喜ぶオーナーもいれば、外国人店員の登場で仕事を奪われたと思う日本人もいるかもしれない。日本人ファーストの思いを持つ人は外国人労働者を苦々しく思う人もいるに違いない。あらためて言葉を入れ替えてみると、驚くほど似た構造になっていることに気づかされた。
私は、野球選手もコンビニ店員さんも、ひたむきに仕事に向き合ってくれたら、置かれた社会にしっかり貢献してくれたら、同じではないかと思う。
イチローがメジャーリーグの監督になる日があれば、漆塗りを外国人職人から日本人が学ぶ日も来ると思う。人口減少が著しいわが国ではいずれ、たとえ日本の企業であっても外国の人から仕事を教えてもらうようになることが容易に想像できる。
〇〇人ファーストの思いが強くなれば、その機会を減らすことにつながりかねない。日本の企業で外国人の上司から学ばないという思いは、イチローをメジャーリーグの監督にさせないという思いと近いかもしれない、と私は思う。
一方、大相撲をみると、横綱を始め上位に外国人力士が名を連ねる。相撲は日本伝統の文化であり日本の国技だが、相撲界は意外と外に開かれていると感じざるを得ない。“多文化共生”と表現するのは簡単だが、実践は難しいとよく耳にする。しかし、意外に私たちの近くや心持ちにあるようなことかもしれない。これは一人のスポーツファンとしての日常の気づきです。
私は、日本人メジャーリーガーも外国人力士も、日本のコンビニで働く外国人店員さんも、皆にエールを送りたい。
《神田相談員について》
https://okayamas.johas.go.jp/consultation/advisor-profile/#kanda_hideyuki
秋になると・・・(山下龍子相談員)
庭に赤い萩の花が咲き、夜になると虫たちの声が聴こえてくる。
そのような日にはチャイコフスキーのピアノ曲「四季」から「秋の歌」を聴きたくなる。この曲は1875年(35歳)にロシアの雑誌の編集者から「毎月1曲ずつ連載用の小品を書いてほしい」と依頼されて作曲した、「四季」という曲集の中の一つだ。各月の曲にロシアの詩人の詩句を添えている。10月は、アレクセイ・トルストイの次の一句だ。
「秋よ、わたしの悲しみよ、君の涙がそっと地上に落ちて、静けさが野を覆う。」
この詩のように曲にも秋の静けさ・寂しさ・悲しさが感じられる。冒頭から静かで内に沈み込むような旋律が流れる。秋の静けさや物思いにふける人の心を表しているようだ。日本の秋は米が実り、柿が色付き、栗が熟す収穫の季節だ。秋祭りの囃子が聴こえ、子供たちの声が賑やかだ。北の国では秋は悲しい季節なのだろうか、と思ったが、調べてみると、この曲想はチャイコフスキー独特のものであったようだ。
「秋の歌」の作曲の前年の1874年に名作「ピアノ協奏曲第1番」が酷評され、彼は自信を失っていた。友人への手紙には次のように書かれている。
「私は無能です。作曲家としての道を歩むべきではなかったかもしれません。」
彼は裕福な家庭に生まれたが、母は情愛に乏しく幼いころから愛情に飢えていた。14歳で母が亡くなると、少年は「世界が終わった」と感じ、以後ずっと「愛されたい」という思いを抱え続ける。
1877年(37歳)の時にかつての教え子アントニーナ・ミリュコワと結婚するが、2か月で破綻し、別居状態のまま生涯を終える。当時のロシア社会では、独身の男性は「社会的に不完全」とみなされたために望まない結婚をしてしまったのだ。
傷ついたチャイコフスキーは、「心のつながり」だけは強く求め続け、パトロンのフォン・メック夫人とは13年間、実際に会うことはなく書簡関係だけを続けた。「現実で会えば、関係が壊れてしまうかもしれない。」と恐れたからだ。彼の繊細な心と人間関係への不安が表れているエピソードだ。
「秋の歌」の美しい旋律はチャイコフスキーが秋という季節に自分の感情を投影し、それが聴く人の心に深く響いてくるのだなと思った。
《山下相談員について》
https://okayamas.johas.go.jp/consultation/advisor-profile/#yamashita_ryuko
研修会のご案内
研修会についてはこちら
https://okayamas.johas.go.jp/training/
産業医研修会についてはこちら
https://okayamas.johas.go.jp/category/training/ipt/
岡山地方産業安全衛生大会
日時:令和7年11月4日(火)13:00~16:45
場所:岡山コンベンションセンター(岡山駅から徒歩4分)
産業安全・労働衛生の関係者が一堂に集い、事例発表や専門家による講演などを行う、岡山県内最大の安全衛生イベントです。産業現場での安全と健康を誓う安全文化の祭典に、ぜひご参加ください。
※参加無料、相談コーナー、機器・保護具展示コーナー等あり
岡山産業保健総合支援センターは、12:00から「相談コーナー」を開設します!
■プログラム
どん底からの会社再建~過疎地域の雇用を守り、働く人を大切にする職場づくり~
(協栄金属工業株式会社 代表取締役社長 小山久紀氏)
あぶない!靴・床面・動線から転倒リスクをズバリ物申す!
(岡山県+SAFE協議会 岡山労働局・日進ゴム株式会社・株式会社丸五)
最近の労働安全衛生行政から
(岡山労働局労働基準部 健康安全課長 貞宗恵治氏)
https://okayamas.johas.go.jp/r7_aneitai/
「産業保健21」が発行されました
https://okayamas.johas.go.jp/21-122/
情報誌『産業保健21』は、産業医をはじめ、保健師・看護師、労務担当者等の労働者の健康確保に携わっている皆様方に、産業保健情報を提供することを目的として、独立行政法人 労働者健康安全機構が発行しています。
特集:災害に対応する危機管理体制とは
インタビュー産業医に聞く:産業保健における「主役」は従業員と会社・産業医として「脇役」に徹した活動を
労働衛生対策の基本:腰痛対策とその実践
津波による行員らの死亡につき銀行の安全配慮義務違反が否定された事案(七十七銀行(女川支店)事件)
など
オンデマンド配信「働く女性の健康課題等に関する研修会」
女性の健康課題や母性健康管理ついて、専門家の解説や事例検討のほか、企業による事例発表から、女性の健康支援の具体的な対応事例も学べます。
配信期間:令和7年10月22日~令和8年3月15日
■働く女性の心とからだの応援サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/kenshu2025/
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)からのご案内
~第33回職業リハビリテーション研究・実践発表会~
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構においては、職業リハビリテーションに関する研究成果等を広く各方面に周知するとともに、参加者相互の意見交換や経験交流を目的として、「職業リハビリテーション研究・実践発表会」を毎年開催しています。
今年(第33回)は、11月12日(水)および13日(木)の2日間、東京ビッグサイトにて開催を予定しており、現在ホームページにて参加申込みを受け付けています(参加費:無料)。
申込締切は令和7年10月13日(月・祝)13時までで、定員に達したプログラムから順次締め切りとなります。参加をご希望の方は、どうぞお早めにお申込みください。
■独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
https://www.nivr.jeed.go.jp/vr/news/vrhappyou33-history.html
Zoom/YouTube「中小企業におけるメンタルヘルス対策~ストレスチェック義務化への対応~」
日時:11月13日(木)13:30~16:30
小規模事業場にもストレスチェックが義務化されます。
メンタルヘルス対策に積極的に取り組む中小企業の取組内容や考え方を参考にして、自社にあった進め方について考えましょう。
オンライン開催、参加無料です。
基調講演
「職場のメンタルヘルス対策を改めて考える~自発性と専門職の活用~」
■働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/mental_sympo/2025/