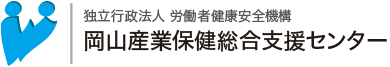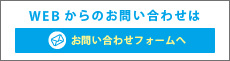相談員便り
マーフィーの法則(徳弘雅哉相談員)
先日、他社の安全衛生委員会で「ハインリッヒの法則」についてコメントしていたときのお話です。
“重大災害1件の背景には29件の軽微災害、その背景には300件のヒヤリ・ハットが存在する。重大災害を防ぐために、ヒヤリ・ハット、つまり小さな問題も軽視せずに対策を立てなさい。“という、例のあれです。
その時、思い出しました。“ハインリッヒの法則・・・法則・・法則・・・、昔、「マーフィーの法則」って流行ったよな…何だっけ?”と。
中学の時、隣の席のA子さんは、雨が降れば「いやぁ!マーフィーの法則!」、宿題忘れたら、「いやぁ!マーフィー!」、テストの点数が悪かったら、「マー!(以下割愛)」。良く知らなかったので、「マーフィーって誰よ。いや、人?モノ? 概念?A子さんそんなに傾倒して大丈夫?」と思っていたものです。
気になったので、この年にして初めて調べてみることに。『MURPHY’S LAW』(英語版)という本を取り寄せました。到着した本は、半裸の軍人的な男女がライフル銃構えているワイルドなイラストが表紙。これ絶対危険なやつ。
A子さんが「マー!(以下割愛)」していたのは30年ほど前ですが、「マーフィーの法則」の起源とされているのは1950年頃のようです。
アメリカのエドワード空軍基地で、John Paul Stapp少佐が飛行試験中に装置の異常を検知し帰還。Edward Aloysius Murphy Jr.というエンジニアが原因を調査すると、誰かが間違った配線(16のセンサーが全て逆向き!)をしていたことが分かりました。
その時、Murphy Jr.が言ったそうです。「いくつかの方法があって、1つが悲惨な結果に終わる方法であるとき、間違う人はそれを選ぶだろう」と。Stapp少佐がこの話を紹介したところ、基地内外で話が広まっていき、一般化しました(という説が一番有力)。
1977年、『Murphy’s Law and Other Reasons Why Things Go WRONG』が出版され、ベストセラーになりました。
我々が見たり聞いたりしているのは、Murphy「的」な事象や法則を他者が集めたり発表したりしているもののようですが、元々は「常に最悪のシナリオを想定しておく必要がある。」というリスク管理の概念に端を発したものでした。これ結構まじめなやつ。
現代で言うところのフールプルーフ(誤操作が発生しないようにする設計)やフェイルセーフ(事故が起きても被害を最小限にする設計)、もしくは(原子力安全でよく聞かれる)深層防護の観点にも通じるものがあると思われました。さて、この本は選択的記憶、認知バイアス、確証バイアスなどの話に続きますが、こちらは割愛します。
おそらくMurphy Jr.は言っていませんが、このような法則も紹介されていました。
“傘を持っていない日に限って雨が降る”、“忘れ物をしないように念入りにチェックすると別の物を忘れる”、“完璧だと思った資料に、提出後必ず誤字が見つかる”。…A子さん…間違っていない…。
ちなみに私、『MURPHY’S LAW』(英語版)を購入する前に、Joseph Murphyという学者の本を間違って買ってしまいました。「いやぁ!マーフィー!」と、よい感じでオチるかと思いましたが、潜在意識、ポジティブシンキングなどの内容で、こちらの本も大変有意義、勉強になりました(ポジティブシンキング)。
三菱自動車工業株式会社
徳弘
■徳弘相談員について
https://okayamas.johas.go.jp/consultation/advisor-profile/#tokuhiro_masaya
ストレスチェック10年、そして義務化へ(難波靖治相談員)
ストレスチェック制度が導入されてから10年が経過し、職場におけるメンタルヘルス対策の一環として、徐々に定着しつつあります。
この制度の目的は、労働者自身が自身のストレス状況を把握し、必要に応じて医師との面談を通じて早期に対処することで、メンタル不調の予防を図ることにあります。また、努力義務ではありますが、職場で集団分析を行い、その結果を職場環境の改善に活用することも、制度の重要な意義のひとつです。
実施状況を見ると、近年では従業員50人以上の事業場の95%以上が年1回の実施を定例化しており、受検率が8割を超える事業場は約78%に達しています。特に中規模以上の事業場では、多くの従業員がストレスチェックを受検している状況です。
一方で、高ストレス者と判定される割合は業種によって異なり、概ね5~20%とされていますが、そのうち医師による面談指導を申し出る割合は5%未満にとどまっています。さらに、集団分析を実施している事業場は85%にのぼるものの、それをもとに職場環境改善活動を行っている事業場は50%弱にとどまっています。
つまり、ストレスチェック制度は一定規模の事業場では定着しているものの、高ストレス者が医師面談に至るケースは少なく、集団分析の結果を職場改善に活かしている事業場も半数程度にとどまっているのが現状です。制度は広まりつつあるものの、その活用にはまだ改善の余地があると感じています。
こうした中、ストレスチェックが今後3年以内に従業員50人未満の事業場でも義務化されることとなりました。これに伴い、小規模事業場におけるストレスチェック実施の課題について考える必要があります。
まず1点目は、ストレスチェックの実施前に衛生委員会で体制や方法を審議することが求められますが、小規模事業場には衛生委員会の設置義務がなく、制度の周知や個人情報保護に対する懸念が払拭できるかが課題となります。
2点目は、制度を理解した実施者や事務従事者の確保が難しいことです。従業員数が少ない中で、制度運用に必要な人材を確保するのは容易ではありません。
3点目は、高ストレス者が医師面談を希望した場合に、面談を実施できる医師を確保できるかという点です。地域産業保健センターの活用も考えられますが、実際の職場を知らない医師が面談を行い、就業上の措置を判断することには限界があると考えられます。
また、ストレスチェック後の集団分析と職場環境改善は努力義務とされていますが、50人以上の事業場での集団分析実施率が52.1%であるのに対し、10人から49人の事業場では17.3%にとどまっています。職場環境改善には、従業員の積極的な協力が不可欠であり、人的資源やノウハウが限られる小規模事業場では、外部からの支援がなければ実施は困難と思われます。しかし、その支援を担える資源も十分とは言えない状況です。
さらに、労働者のプライバシー保護に配慮した集団分析を行う必要があり、その点でも小規模事業場では対応の難しさが予想されます。
今後は、小規模事業場でも安心して制度を活用できるよう、周囲の支援や工夫を通じて、少しずつ環境を整えていくことが大切だと感じています。
■難波相談員について
https://okayamas.johas.go.jp/consultation/advisor-profile/#nanba_seiji
研修会のご案内
研修会についてはこちら
https://okayamas.johas.go.jp/training/
産業医研修会についてはこちら
https://okayamas.johas.go.jp/category/training/ipt/
オンライン配信:2026年4月1日努力義務化!
治療と仕事の両立支援~中小企業における取組のヒント~
治療と仕事の両立支援シンポジウムを開催します。
オンライン配信あり、視聴無料です。
■配信開始予定日:2025年12月24日(水)
■基調講演
「治療と仕事の両立支援を行う際の流れや医療機関との連携の重要性について」
(がん研究会有明病院 麻酔科 副医長サバイバーシップ支援室両立支援グループ長 升田 茉莉子 氏)
■事例発表・パネルディスカッション
両立支援のための休暇制度について
両立支援に関する意識啓発について
相談窓口等の明確化、体制整備について
産業保健総合支援センターについて
■治療と仕事の両立支援ナビ(厚生労働省)
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/symposium/
労災疾病等医学研究「高血圧性心疾患」について
近年、心不全患者が急増していますが、その原因は多岐にわたります。高血圧が原因の心不全では、心収縮能は保たれているにもかかわらず拡張機能が低下する例と、極端に心機能が低下する例が認められています。
令和6年度から開始した研究「左室駆出率が低下した心不全を呈する高血圧性心疾患に関連するバイオマーカーの同定と早期診断・治療戦略の開発」では、心不全を発症した高血圧患者において、特定の遺伝子が心機能低下に関与するかを検討しています。
将来的に心機能の低下が予測される高血圧患者を同定することで重症心不全発症予防に寄与できる可能性があります。
本研究により、現時点では明らかでない高血圧の心筋線維化に及ぼす分子メカニズムが解明できれば、発症予測アルゴリズムの構築、新薬の開発など、さまざまな臨床応用に道を開くことができます。
高血圧を指摘される勤労年代において遺伝子レベルでの解析が進むことで、より早期からの治療介入が可能となり将来的に心機能が低下して発症する心不全のリスクを低減することが期待されます。
本研究詳細については以下URLからご覧ください。
https://www.johas.go.jp/kenkyu/rosaisippei13bunya/tabid/2538/Default.aspx
※これまでご案内していた労災疾病等医学研究普及サイトは、令和7年9月25日に閉鎖し、労働者健康安全機構ホームページ内へ移設・統合いたしました。ご面倒をおかけいたしますが労働者健康安全機構ホームページから情報をご確認いただきますようお願いいたします。
労働者健康安全機構ホームページ「労災疾病等医学研究・開発」
https://www.johas.go.jp/kenkyu/rosaisippei13bunya/tabid/398/Default.aspx